
|教室紹介|お知らせ|利用予定表|教育の中の水泳/連載11| |バックナンバーに戻る|
HOME>教育の中の水泳/連載11

|

富山大学芸術文化学部教授 立浪 勝
岩手県花巻市の宮澤賢治記念館を訪れました。賢治は、「雨にもまけず」の詩で有名ですが、私は「生徒諸君に寄せる」の詩が一番好きです。どのような詩か、最初の1節を紹介します。
この四ヶ年が わたくしにどんなに楽しかったか
わたくしは毎日を
鳥のやうに教室でうたってくらした
誓って云ふが わたくしはこの仕事で
疲れをおぼえたことはない
賢治が教壇を去るときに読んだ詩ですが、“教師としての仕事で、疲れをおぼえたことがない”と言い切れる真剣さ、誠実さに心を打たれるのです。
花巻市を訪れた目的のひとつは、賢治の作品に出てくるイギリス海岸を見たかったからです。宮澤賢治の作品「イギリス海岸」には、水泳に関する場面が多く、大正中期の水泳事情がよくわかります。「イギリス海岸」の文章を引きながら、当時の様子を紹介したいと思います。
『夏休みの十五日の農場実習の間に、私どもがイギリス海岸とあだ名をつけて、二日か三日ごと、仕事が一きりつくたびに、よく遊びに行った処がありました。』
実はイギリス海岸とは海ではなく、賢治が勝手に名づけた花巻市内を流れる北上川の西岸の一部です。賢治はここへよく生徒を連れて遊びに行きました。
『町の小学校でも石の巻の近くの海岸に十五日も生徒を連れて行きましたし、隣の女学校でも臨海学校をはじめていました。けれども私たちの学校ではそれはできなかったのです』
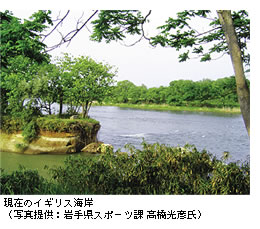 賢治がイギリス海岸に生徒を何度か引率していったのは大正11年ですから、すでに東北の岩手県でも小学校などでは臨海教育が始まっていたことがわかります。しかし、賢治の勤める農学校では臨海教育は実施していませんでした。賢治の水泳の腕前はどの程度かわかりませんが、次のような文から推測すると救助が出来るほどではないが、かなり泳げたようです。 賢治がイギリス海岸に生徒を何度か引率していったのは大正11年ですから、すでに東北の岩手県でも小学校などでは臨海教育が始まっていたことがわかります。しかし、賢治の勤める農学校では臨海教育は実施していませんでした。賢治の水泳の腕前はどの程度かわかりませんが、次のような文から推測すると救助が出来るほどではないが、かなり泳げたようです。
『実は私はその日まで、もしおぼれる生徒ができたら、こっちはとても助けることもできないし、ただ飛び込んで行って一緒に溺れてやろう、死ぬことの向こう側まで一緒についていってやろうと思ってゐただけでした。』
また、川で子供たちが遊ぶのは夏休み中の普通の光景で、安全のため救助を担当する人を配置し、救助ブイも用意されていたようです。
『草の生えた石垣の下、さっきの救助区域の赤い旗の下には筏もちょうど来ていました。花城や花巻の生徒がたくさん泳いで居りました。・・・・・・・救助係はその日はもうちゃんとそこに来ていたのです。腕には赤い巾を巻き鉄梃も持っていました。』
一方、救助を担当する人はかなり責任感が強く、町当局と掛け合って、安全のために救助員の増員か安全浮き具の設置を要求しています。
『この人は町へ行って、もう一人、人を雇うかそうでなかったら救助の浮標を浮べて貰いたいと話しているというのです。』
大正中期、東北の小さな町のことですが、夏休みには川で子供たちが水遊びをしながら水泳を修得していたこと、さらに、安全のために行政がそれなりの手当てをしていたことがわかります。
昭和30年代後半、「よい子は川で遊ばない」という張り紙を見た記憶があります。汚染などの理由で、川で泳ぐことが禁止され始めた頃です。それから長く、川は危険なところでした。最近、親水化という言葉と共に、水辺が再評価されています。賢治のように本物の自然の川で子供を安全に遊ばせる施策が求められます。
「引用は宮澤賢治全集(筑摩書房)」 |
|
|教室紹介|お知らせ|利用予定表|教育の中の水泳/連載11| |HOME|

