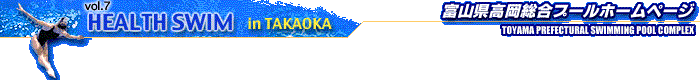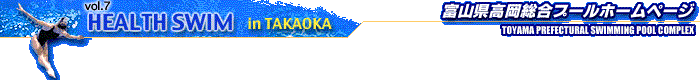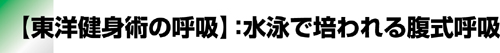
 ヨーガ、太極拳、気功では三つの基本的な方法が共通している。
すなわち身体を整える(調身)、心を整える(調心)、そして呼吸を整える(調息)の三つで、
それらは呼吸法によって得られるとされる。
ヨーガ、太極拳、気功では三つの基本的な方法が共通している。
すなわち身体を整える(調身)、心を整える(調心)、そして呼吸を整える(調息)の三つで、
それらは呼吸法によって得られるとされる。
これは日本の座禅も同じである。
これらの健身術では腹式呼吸が強調されている。呼息と吸息のリズムが大切とされ、深い呼吸を基本とし、
呼吸数を通常の三分の一から四分の一まで減らす。この呼吸法のマスターがそれらの健身術の効果と強く結びついている。
もちろん、西洋的健康法の代表格であるエアロビック運動(ダンス、ジョギング、自転車など)でも酸素摂取という面から、
呼吸法がその効果に深くかかわっている。しかし、エアロビックスの呼吸は、一般に、浅く回数が多い。
この点が深くゆったりした呼吸をおこなう東洋の健身術と根本的に異なる。
このリズムの違いに注目し、それぞれの特徴を調べてみたところ、興味ある結果が示された。
エアロビックダンスとヨーガで、それぞれ最大酸素摂取量の四〇パーセントになる強度の運動中の呼吸回数と内肋間筋の放電量を調べた。
呼吸回数は、もちろんエアロビックダンスのほうが圧倒的に多く、ヨーガの三倍の一分間一八〜二十五回に達した。
しかし、内肋間筋の筋放電をみると、逆にヨーガの方が四〜五倍強い放電量になっていた。
筋放電の強さは、その筋の収縮の強さを示すので、ヨーガの方が四〜五倍強く筋を収縮させ、深い呼吸をしていたことを示す。
このことから、ヨーガは、呼吸回数を減らしながら、一回ごとの呼吸を深く大きくおこなうことで、
トータルの換気量としては同じ運動強度のエアロビックダンスと同等のものを得ることがわかる。
「静」のイメージの強いヨーガでも、体内に取り入れる大気の量は「動」のイメージがあるダンス運動と変わりなかったことになる。
著者 富山県国際健康プラザ・健康スタジアム館長 永田 晟(呼吸の奥義より)
|